イベントレポート
ソラハブ
2026年2月4日
Sora Blog

2025.08.06
今回は、7/28に開催した対談イベントの開催レポートと、次回8月25日(月)の対談イベントのご案内をお送りいたします。
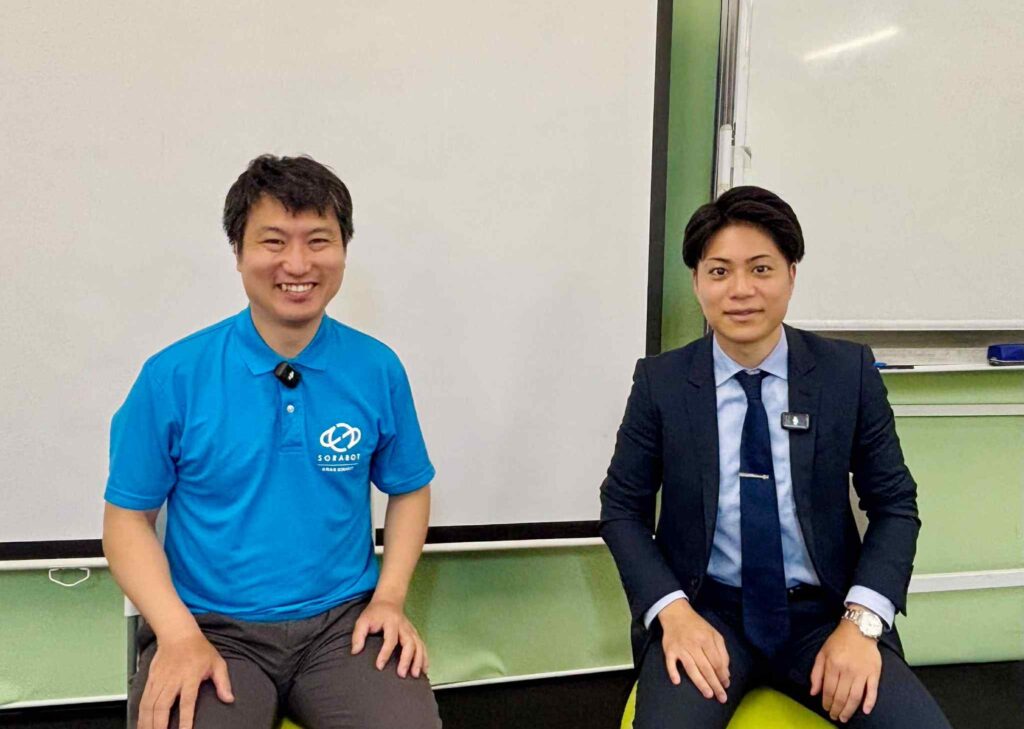
FwriteDown行政書士事務所の代表・本間貴大さんをお迎えし、最新の制度動向と機体の型式認証制度、そして飛行前の手続きや注意点についてお話いただきました。
DJI Mini 4 Proが型式認証を取得してからしばらく経過する中、現場では「飛ばせるつもり」でルールを見落とし、トラブルになりそうなケースや理解の仕方も見受けられます。
本間さんはそのような相談を日々受ける行政書士として、Mini 4 Proの特徴や認証機体としての制限事項を丁寧に整理し、「何ができて、何ができないのか」「飛ばす前に確認すべき要件は何か」について、行政書士の目線で具体的に語ってくださいました。

DJI Mini 4 Proは、2024年春に日本の型式認証を取得した数少ない認証機体であり、改正航空法のもとでの飛行を可能とするモデルとして注目されています。
しかし「型式認証を受けたから自由に飛ばせる」という誤解も多く、実際には細かい条件や、カテゴリーII・補助者なし飛行に関する制約が多く存在します。
本間さんは、型式認証によって「許可・承認不要となる範囲」はあるものの、それが無条件に全ての飛行を可能にするものではない点を強調。
特に飛行場所や条件、プロペラガードの装着要否、飛行高度の上限など、個別の確認事項が多く、理解の浅い方には注意していただきながら、
必要に応じて制度の内容をかみ砕いて伝える「制度と実務の橋渡し役」が求められていると語りました。
2022年末にスタートした国家ライセンス制度(いわゆる一等・二等資格)ですが、制度導入当初の熱狂とは裏腹に、運用上の課題や誤解が散見されているとのことです。
たとえば「ライセンスがあれば、すぐにどこでも飛ばせる」という認識が現場には残っている一方、実際には申請先、飛行エリア、飛行内容の種類に応じて追加の許可が必要になる場面も多く、制度理解の浸透が追いついていない実態があります。
本間さんは、ライセンス制度の本質は“安全のための教育と評価制度”にあることを忘れてはならないと指摘。ライセンスは免罪符ではなく、あくまで「飛ばすための土台」であり、最終的な責任と判断は操縦者自身にあるという視点が重要だと語られました。

対談では、Mini 4 Proの型式認証機体としての“通常のルールとの違い”に焦点が当てられました。
特に本間さんは、飛行記録の付け方(整備手順書)や運用マニュアル(飛行規程)の扱いが通常の機体とは異なることを強調し、「マニュアル(飛行規程)に沿った運用が求められる認証機体だからこそ、内容の把握と携行が必要」だと説明。
さらに、現場で必ず遵守・携行すべき書類(飛行マニュアル、飛行規程、技能証明書など)についても具体的に解説。申請・運用時のルールに加え、飛行中に見せる可能性のある場面を想定し、「見せられる状態にしておく工夫も現場では大切」と語られました。
飛行記録と点検記録の通常運用との違いにも触れて頂き、本間様が提供されているドローン運用管理システムの「FwriteDown 」についてもご紹介いただきました。
Mini 4 Proのような認証機体の正しい運用には、制度の理解と書類管理の両面が欠かせず、これまでの“慣れ”とは違う対応が求められていることが共有されました。

最後に本間さんより一緒に仕事をしたい仲間についてお聞きしました。
「一緒に仕事をするなら、制度を形式的に守るだけでなく、“なぜそれが必要か”を一緒に考えられる人と関わりたい」
本間さんは、自身の役割は単なる手続き代行ではなく、制度と現場の“意味づけ”を共有することだと考えており、依頼者が現場で直面する不安や曖昧さを一緒に解きほぐし、対話を通じて着実に前進する関係性を築くことを大切にしていると語りました。
制度が整いつつある今だからこそ内容をよく熟読して理解し、自分が飛ばす環境や用途に照らし合わせながら、どう活用すべきかを考える視点が求められます。
今回の対談では、Mini 4 Proという具体的な機体を題材に、制度の解釈や実務運用の工夫まで幅広く共有されました。